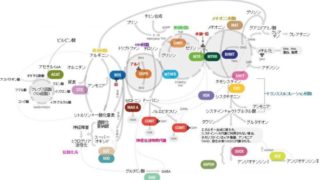 脳機能改善
脳機能改善 「メチレーション」と精神疾患について
栄養療法による精神疾患へのアプローチを考えるとき、「メチレーション」の知識が欠かせません。そこで、この「メチレーション」と精神疾患の関係について、なるべくわかりやすく説明していきます。
脳内の神経伝達の仕組み私たちの脳の中には約千億個もの脳...
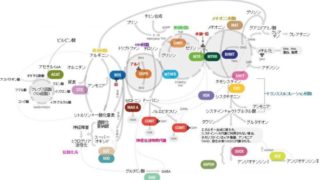 脳機能改善
脳機能改善 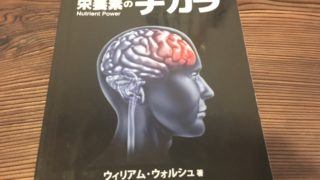 ★おすすめ本
★おすすめ本  副腎機能
副腎機能  ビタミンB群
ビタミンB群 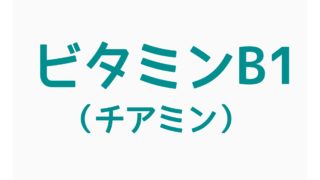 ビタミンB群
ビタミンB群  ミネラル
ミネラル 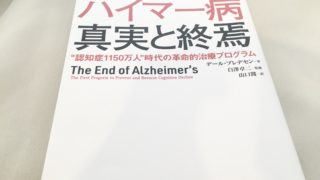 認知症対策
認知症対策  認知症対策
認知症対策  認知症対策
認知症対策  ビタミンC
ビタミンC  ビタミンC
ビタミンC  ビタミンC
ビタミンC  抗酸化・アンチエイジング
抗酸化・アンチエイジング  頭痛を治す
頭痛を治す  ★目的別健康情報
★目的別健康情報  感染症予防対策
感染症予防対策  ★目的別健康情報
★目的別健康情報  抗酸化・アンチエイジング
抗酸化・アンチエイジング  抗酸化・アンチエイジング
抗酸化・アンチエイジング  ★目的別健康情報
★目的別健康情報  腸を元気にする
腸を元気にする  腸を元気にする
腸を元気にする  油について
油について 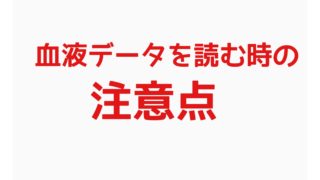 血液データを読むための基礎知識
血液データを読むための基礎知識 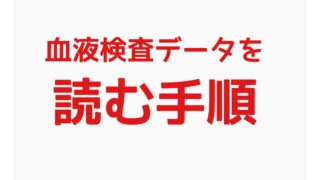 血液データを読むための基礎知識
血液データを読むための基礎知識  ★血液データの読み方
★血液データの読み方 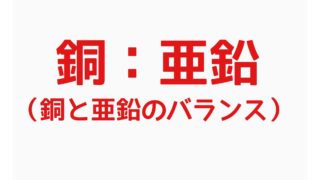 ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★目的別健康情報
★目的別健康情報  血液データを読むための基礎知識
血液データを読むための基礎知識  ★目的別健康情報
★目的別健康情報  ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★目的別健康情報
★目的別健康情報 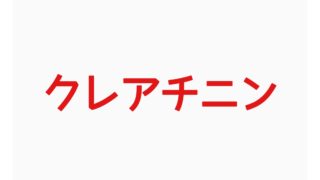 たんぱく質代謝
たんぱく質代謝  ★血液データの読み方
★血液データの読み方 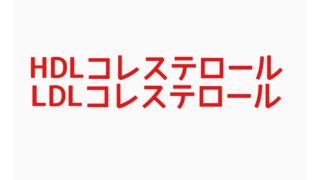 ★血液データの読み方
★血液データの読み方  たんぱく質代謝
たんぱく質代謝 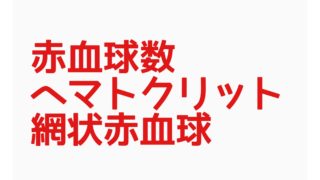 ★血液データの読み方
★血液データの読み方 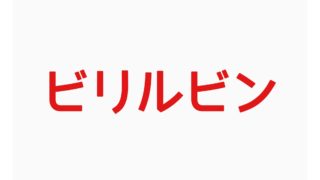 ★血液データの読み方
★血液データの読み方 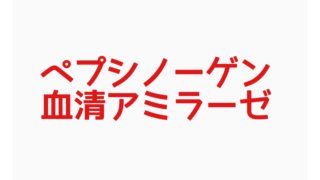 ★血液データの読み方
★血液データの読み方  たんぱく質代謝
たんぱく質代謝  ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★目的別健康情報
★目的別健康情報 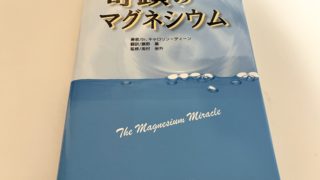 ★目的別健康情報
★目的別健康情報  ★血液データの読み方
★血液データの読み方 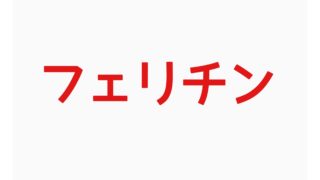 ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★血液データの読み方
★血液データの読み方  ★目的別健康情報
★目的別健康情報 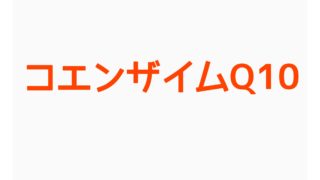 コエンザイムQ10
コエンザイムQ10