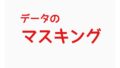AST・ALTとは
血液検査の項目を見ると、AST(GOT)・ALT(GPT)という項目がありますね。
この二つの項目を、栄養学的に読み取る方法について説明します。
ASTとALTは、どちらもたんぱく質代謝に欠かせない酵素です。
ASTは、「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ」(またの名をGOT=「グルタミン酸オキザロ酢酸トランスフェラーゼ」)
ALTは、「アラニンアミノトランスフェラーゼ」(またの名をGPT=グルタミン酸ピルビン酸トランスフェラーゼ )
という、なんだか舌を噛みそうな名前の略になります。
昔はGOT・GPTの呼び名が使われることが多かったのですが、最近はAST・ALTの呼び方が主流です。
ちなみに、ASTやALTの単位は「U/ℓ」。
これは、酵素活性を表す単位です。U/ℓの単位が付いている項目は、酵素を見ているのだということがわかります。
酵素はたんぱく質によってできていますので、たんぱく質不足があれば当然、酵素群は低下します。
ASTとALTは、臓器によって含まれる量が異なります。
その違いをざっと説明すると、
・ASTとALTはともに、肝臓や腎臓に多く含まれている
・ASTは心筋や骨格筋・血球といった、ミトコンドリアが多い器官にも多く含まれる
・ALTは特に肝臓に多く含まれる
このような特徴があります。
二つは似たような名前で混同しやすいのですが、覚えやすい語呂合わせがあります。
AST=Sは「し」んぞうのS
ALT=Lは、「レ」バーのL
と覚えておきましょう♪
AST・ALTとビタミンB6
ASTとALTはたんぱく質を作る時に必要な酵素ですが、この時に特に重要となる栄養素があります。
それは、ビタミンB。
ビタミンB6はASTとALTの「補酵素」として働きます。
つまり、たんぱく質代謝が正常に行われるには、ビタミンB6が欠かせないということです。
(ビタミンB6はその他の様々なアミノ基転移酵素の補酵素として働くのですが、その中でも特にALTとASTの活性が高いと言われています)
AST・ALTの数値からわかる事
通常の健康診断でAST・ALTの値は「問題なし!」と言われた場合でも、もっと細かく見ていくと、色々なことを読み取ることができます。
ASTやALTの数値が高くなるということは、ASTやALTが含まれる器官の細胞が壊れて、酵素が血液中に流れてきたということが予測されます。
そのため、生活習慣病で肝臓などが疲れている場合は、この二つの値が高くなります。
ASTとALT値が正常の範囲内にあって、他の肝機能や心機能を示す値に問題がないとき(つまり内臓の機能に病的な問題がない場合)、単に内臓の具合をみるだけでなく、ビタミンB群(特にビタミンB6)が体内で有効に使われているかの重要な指標となるのです。
この二つの数字は、20ぐらいで同じ数値になっている状態が一番理想的なのですが、どちらかが高かったり低かったたりすることで、色々なパターンを推測することができます。
そのパターンについてまとめると、次のようになります。
①AST=ALT 20・20~22・22ぐらい・・正常
前述した通り、二つの値が20~22ぐらいで、差は0~1と、ほぼ同じ値でそろっているのが一番理想的なパターンです。
(ただし、後述する②+④の状態があると一見①に見えることもあるため注意が必要です)
②AST>ALT 差が2以上で、両者ともに低い・・ ビタミンB群代謝不足・低血糖
ASTとALTはビタミンB6を補酵素とする酵素であるため、たんぱく質またはビタミンB6の欠乏で低下します。
ASTよりもALTの方が代謝のスピードが速いので、ビタミンB6が不足すればするほど、ALTの低下が顕著に表れるようになります。
つまり、ALTの方がビタミンB6不足の影響を受けやすいということです。
そのため、GPTとGOTの差がどんどん開いていくことになります。
つまり、2つの数値の差が大きいほど問題があると考えられます。
例えば、ASTとALTがともに一桁または10台前半であれば、たんぱく質やビタミンB6がかなり不足していると考えられます。
さらに、ALTは低血糖時の糖新生の際に必要な酵素ですので、この酵素が低い人は低血糖を起こしやすい状態になっていることが予測されます。
③AST<ALT または両者ともに高め(ASTとALTがともに30ぐらい) ・・脂肪肝、ウイルス性肝炎、慢性肝炎
ASTよりもALTが大きくなっている場合=「脂肪肝パターン」です。
特に、ALT(GPT)は肝臓にそのほとんどが存在するため、診断特異性が高いのです。
本来、脂肪肝かどうかは直接肝臓を画像で見て診断されますが、この方法では画像診断ではわからない段階での隠れ脂肪肝に気づくことができます。
脂肪肝だけでなく、ウイルス性肝炎などによる肝機能障害でもALTの値が高くなります。
尚、脂肪肝があると、中性脂肪やコリンエステラーゼも高めにでやすいです。
脂肪肝は肝臓の炎症ですので、炎症によって高値になるフェリチン値にも影響を与えることになります。
「脂肪肝」といえば、アルコールの飲み過ぎが原因だと思っている人は多いと思いますが、実は脂肪肝の原因はアルコールだけではなく、糖質の摂りすぎによっても起こりやすいです。
従って、普段の食生活で糖質ばかり摂っているという方は要注意です。
④AST>40 ASTだけ数値が高い場合・・心臓疾患、筋肉の障害など
ASTは心筋などにも含まれるため、ASTだけが高い場合は心臓や筋肉の組織が壊れたと判断され、肝臓以外の病気の可能性が考えられます。
(筋肉の障害、心筋梗塞、溶血性貧血、肝硬変、筋ジストロフィー、胆石、胆のう炎、胆道がん、膵臓癌、アルコール性肝障害など)
⑤AST↑ ALT↑ ・・ 肝臓、胆道系の病気が考えられる
二つの値が高い場合は、肝臓や胆道系の病気が考えられます。
この場合、γ‐GTPやALPも共に高値が見られるようになります。
値が高いからと言ってビタミンB6が足りているかというと、そういうわけではなく、この場合も、ビタミンB群の消費が増大していると考えらえます。
ビタミンB6の不足について
次に、②のパターンの、ビタミンB6不足の状態についてもう少し深堀りしていきたいと思います。
ビタミンB群は網羅的に代謝に携わっているため、B6の不足が予測されるということは、B群が総合的に不足しているということが考えられます。
ビタミンB群は、摂取した糖質をエネルギーに変えたり、神経系を健やかに保ったり、アルコール分解に関与したりと、代謝全般に関わる重要な栄養素であるため、ビタミンB群の代謝をみれば、身体がどのくらい正常に機能しているかがわかるのです。
ビタミンB群不足だとミトコンドリア機能は低下し、身体が疲れやすくなってしまいますし、身体の免疫力が落ちてガンなどの病気にもかかりやすくなってしまいます。
従って、ビタミンB6が不足しているからと言ってB6だけを摂ってもあまり効果的ではなく、ビタミンB群複合体(ビタミンBコンプレックス)での摂取が望ましいと考えられます。
↑こちらは栄養療法の医師にも人気の高いTHORNEシリーズのビタミンBコンプレックスのベーシック版。
今は質の高いサプリメントを簡単にネットで買うことができて便利ですよね。
ただ、サプリメントはとても便利なアイテムですが、サプリに頼るだけでなく、ビタミンB群の不足の原因も考えることも大切です。
ビタミンB群が不足してしまう原因は、ビタミンB群の摂取不足だけではありません。
特に注意したいのが、腸内環境の悪化です。
なぜなら、ビタミンB群の多くは腸内で作られるからです。
AST・ALTの数値を見てB6不足が予測される場合、腸内環境が悪い可能性はかなり高いと言えるでしょう。慢性的な下痢や便秘がある場合は、確実に腸内環境は悪いです。
アルコールはビタミン・ミネラルを消耗しますので、アルコールをたくさん飲むという人も、かなりの確率でビタミンB群の欠乏に陥っている傾向にあるため要注意です。
また、B6は神経伝達物質の生成にも関わるため、不足すると睡眠障害(眠れない、眠りが浅いなど)やいやな夢を見る原因にもなります。
B6不足が原因で落ち着きがなくなり興奮しやすくなったりすることもあります。
ビタミンやミネラル不足が子どもの「キレやすい」状態を引き起こしているケースもとても多いです。
⇓ビタミンB6不足の症状についてこちらでも解説しています

AST・ALTのデータを見る時の注意点
ASTやALTは、「マスキング」の多い項目なので注意が必要です。
体調不良があるのに、ASTやALTの値が正常値の場合は、組織障害(肝臓またはそのほかの組織)によって、値が本来よりも上昇しているという可能性が考えられます。
例えば、脂肪肝やウイルス性肝炎のように肝臓に負担がかかっている場合には、特にALTの方が上昇度合いが大きくなるので、脂肪肝が強くなると、偶然20付近に2つとも揃ってしまうということがあるのです。
そのため、食事や他の状況からB6不足が明らかなのに、2つの値が低下していない場合は、脂肪肝と相殺されてこのような数値が出ていると推測する必要があります。
また、AST、ALTは、降圧剤を飲んでいる場合、降圧剤の種類によっては高値になるということも考慮しましょう。
手術の麻酔や、風邪を引いたときにも上昇することがあります。